筆者:酒井環さん(JICA海外協力隊 ジョージア・コミュニティ開発隊員)
プロフィール:
さかい・たまき 長崎市出身。大学1年の講義で核問題に興味を持ち、国内外で平和活動に取り組むナガサキ・ユース代表団の5・6期生。大学卒業後、長崎新聞社に入社。2020~23年度に原爆・平和や米軍基地問題などを取材した。24年に退社後、同年11月から国際協力機構(JICA)海外協力隊(コミュニティ開発隊員)としてジョージアで活動中。
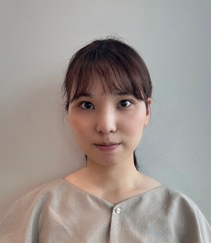
日本から西へ7500キロ、アジアとヨーロッパの境界コーカサス地方に位置する、ジョージア。面積は北海道よりやや小さく、人口約370万人の小さな国です。5千メートル級の山々が織りなす豊かな自然であふれる一方、首都トビリシの街中は西洋風の街並みが広がっています。温暖な気候ゆえに世界最古のワイン生産地としても知られ、世界無形文化遺産にも登録されています。国民性もとてもおおらかで開放的な「陽気な国」です。

他方でその歴史は決して明るいことばかりではありませんでした。その一端が、挨拶に現れています。
「おはよう」などの挨拶には“平和”の意味も含まれているそうです。朝、昼、晩を意味する単語の後ろに、平和を意味する「მშვიდობისა(ムシュビドビサ)」をつけます。おはようは、「დილა(ディラ/朝) მშვიდობისა(ムシュビドビサ/平和)」になります。昼、夜の単語にも、同じようにმშვიდობისა(平和)をつけると、昼と夜の挨拶になります。このほかにも、伝統的な宴会「スプラ」では、国や家族の平和を願い、何度も乾杯します。
コーカサス地域は、様々な大国が覇権争いをする舞台になってきました。東のモンゴル帝国、西のローマ帝国、北のロシア帝国――。ソ連崩壊により1991年に独立を果たしましたが、2008年のロシアの軍事侵攻で、現在も領土の約20%が占領されています。地元の方々も「常に、あらゆる方面から侵略され続けてきた」と口をそろえて話していました。
戦争が身近にあった歴史から、ジョージアでは日常生活でも、平和の願いが映し出されているように感じています。その一つが「挨拶」です。「穏やかな日常は当たり前じゃない。『今日も平和な朝を迎えられたね』という願いを込めている」。ロシアの軍事侵攻を経験したジョージア語の語学学校の先生は説明してくれました。
ジョージア人の「平和への思い」は行動にも現れています。2025年2月25日夜、首都トビリシでは、ロシアによるウクライナ軍事侵攻への抗議デモがありました。参加した市民約3万人が掲げていたのは、ウクライナとジョージア両国の国旗。「国は違えど思いは一つ」。おおらかな国民性ではあるものの、「平和」に対する強い信念を感じました。

そしてその視線は、遠く離れた日本へも向けられていました。彼らと雑談する中で、私が長崎市出身であることを伝えると、お年寄りから若者まで、多くの人から「あなたのおばあちゃんは大丈夫だった?元気にしているの?」と声をかけられ、被爆者らを思って胸に手を当ててくれました。広島、長崎への原爆投下から今年で80年を迎えますが、ジョージア人にとっては、決して過去のことではないのです。
日本を思い返すと、先の戦争を経験した人、広島や長崎での被爆の実相を知る人は年々減り、日本人にとって戦争はもはや過去のものと受け止める人もいます。いかにして被爆者らの記憶を、戦争の悲惨さを継承するか。生まれ育った長崎で記者をしていた私が、これまで向き合ってきた課題でした。普段の挨拶から「平和」を口にし、隣国の惨禍を憂い、7500キロも離れた国の人々をも気にかける――。大きな課題に向き合うヒントを、ジョージアのみなさんからもらえた気がしています。

